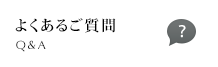大学生に潜むトラブルと効果的な対処法
「自分はトラブルに巻き込まれないだろう」と、普段はそう思って過ごしている人がほとんどかもしれません。しかし、もしもの時に備えてトラブルの対処法や関連情報を知っておくことは、被害を未然に防ぐ確率を高めることにつながります。
自分の身は自分で守る「自己管理・自己防衛」をしっかり行いましょう。もしトラブルに巻き込まれてしまったり、その危険を感じたりした場合は、決して一人で抱え込まず、すぐに警察等、しかるべき窓口に相談してください。
■カルト団体への注意喚起
大学のキャンパス内やその周辺では、「サークル」を装って大学生を勧誘する宗教団体が存在します。特に新入生や下宿生がターゲットにされることが多いです。これらの団体は、音楽、スポーツ、ボランティア、自己啓発、国際交流といった名目で勧誘したり、楽しそうなイベントや合宿への参加を促したりして、巧妙に近づいてきます。
当学でも、学生の下宿先を突然訪れてアンケート記入や団体への勧誘を行う事例や、過去には大学敷地内で卒業生を名乗って声をかけ、勧誘していたケースも報告されています。通信教育課程の皆さんも、スクーリングなどでキャンパスにお越しの際は十分ご注意ください。
勧誘の手口
・サークル勧誘やアンケート調査だけでなく、何か物を尋ねるなどして声をかけてくる。
・世間話や趣味などの話題から親しくなり、住所、電話番号、メールやLINEのIDなどの個人情報を聞き出す。
・メールやLINEでの交流、お茶や食事の機会を設けるなどして、徐々に団体の理念を刷り込んでいく。
・セミナーや合宿に参加するように勧める。
こんな「勧誘」には要注意!
以下のような言葉で誘われたら警戒しましょう。
・「幸福や命について考えませんか?」
・「アンケートに協力してください」
・「友達になってください」
・「日本語教えてくれませんか?」
・「留学生との交流ができますよ」
・「ゴスペルに興味はありませんか?」
・「英会話サークルに入りませんか?」
・「ヨガや占いなどに興味はありませんか?」
・「就活のアドバイスをしてあげる」
・「悩みがあるなら相談に乗るよ」
トラブルに巻き込まれないために
・団体名と活動実態が違うサークルは要注意です!
・「おかしい」と感じたら、きっぱりと「必要ありません」と断りましょう。
・友人や家族に相談する。
・情報操作や情報規制をされたら相手にせず、すぐにその場から離れましょう。
・下宿先を訪問してきても、相手にしないこと。
・個人情報は安易に教えない。
勧誘時の説明と実態が違うと分かったら、きっぱりと関わるのをやめましょう。理由を説明したり、話し合ったりする必要はありません。黙って連絡を絶つことが重要です。
なお、当学では、学内での宗教勧誘活動を禁止しています。万一勧誘された場合、または学内で不審な言動を目撃した場合は、すぐに教職員に連絡してください。
カルト団体による被害に遭われた方、あるいはそのご家族からの相談を受け付けている窓口がいくつかあります。状況に応じて適切な窓口に相談することが大切です。
参考
法テラス:https://www.houterasu.or.jp/
全国霊感商法対策弁護士連絡会:https://www.stopreikan.com/
■悪質商法に注意
学生をターゲットにした悪質商法は後を絶ちません。「突然メールが送られてきた」「SNSで知り合った人と街で会って」など、様々な手口で高額な商品を購入させようとする、いわゆる「悪質業者」が存在します。
近年では、学内・学外を問わず、サークルの勧誘を装って声をかけ、名前や住所、電話番号、メールやLINEのIDなどを聞き出そうとするケースも報告されています。「簡単にもうかる」「いい話がある」などと誘ってくる、正体不明の団体によるアンケートや募金などで個人情報の記載を求められた際は、特に注意が必要です。
事例(当学学生が実際に被害にあったケース)
SNSを通じて知り合った人から投資セミナーに誘われました。「すごい人を紹介してあげる」と言われ、実際に投資で儲けている状況を説明された後、投資用教材の購入を勧められました。「お金がない」と伝えると、「学生ローンを借りればいい」と消費者金融を紹介され、そのまま借り入れをしてしまいました。
被害に遭わないために
・むやみにアンケートなどに応じない。特に住所や電話番号の記入には注意しましょう。
・“おいしい話”だと感じたら十分に警戒し、自宅や路上で勧誘を受けても、必要ない場合はきっぱりと断ること。
・その場では契約せず、家族や友人に相談してみる。契約書や申込書の内容を十分に理解し、契約内容が明確に記載された書面を受け取る。
・サインや押印は簡単にしない。身に覚えのない請求は無視すること。
・学生証の管理をきちんとし、安易に他人に預けない。紛失した場合は速やかに警察に遺失物届を出す。
万が一被害に遭ってしまったら、すぐに「悪質商法110番」や「国民生活センター」、「消費生活総合センター」などに相談しましょう。
参考
・全国の消費生活センター等:https://www.kokusen.go.jp/map/
クーリング・オフ制度について
クーリング・オフとは、訪問販売や電話勧誘販売など特定の取引において、消費者に一定の熟慮期間を与え、その期間内であれば一方的に契約を解除できる制度です。不本意な契約をしてしまった場合、契約書面を受け取った日を含めて8日間または20日間以内(契約の種類によって異なります)であれば、無条件で契約を解除できます。ただし、通信販売や店舗販売で購入した商品はクーリング・オフの対象外となるため注意が必要です。
クーリング・オフの方法
・必ずハガキなどの書面で行いましょう。
・その契約をやめたい旨を書いて、両面をコピーします。
・郵便局の窓口で「簡易書留」「特定記録郵便」または「内容証明郵便」として事業者に送ります。(クレジット契約で購入した場合は信販会社にも送る)
・窓口で書留・特定記録郵便物の記録として、受領証を受け取ります。
・この受領証とハガキのコピーが、クーリング・オフを行った証明となります。
クーリング・オフの方法が分からない、業者とトラブルになった、自分でどうすればいいか迷っている場合は、一人で悩まずに上記の専門機関に相談しましょう。
■アルバイト先でのトラブル(ブラックバイト)
過酷なノルマ、残業や過密シフトの強要など、「ブラックバイト」の問題が増加しています。雇用契約書の内容を必ず確認し、納得した上でサインすることが重要です。
事例(当学学生から実際にあった相談)
チェーン店の宅配ピザ屋でアルバイトをしていた学生が、店長のひどい対応に悩んでいました。ミスをすると暴言を吐かれ、シフトに入れないと言うと恫喝や嫌がらせをされました。アルバイトを辞めたいと申し出ると、「君が辞めることで店に損害が出る。責任を取れ!」と言われたそうです。
このような場合…
法律上、退職したい日の2週間前までに辞めることを伝えれば問題ありません(民法第627条)。これは、万が一バイト先から引き止められても、退職の意思を伝えてから2週間後には自動的に辞めることが可能であり、どんなバイト先からも退職する権利が認められているということです(ただし、「最低1年勤続」など雇用期間に条件がついている契約の場合は異なります)。
もし「暴言を吐く」「恫喝される」「嫌がらせされる」「無理やりシフトを強要される」などの行為を受け、雇用先が法律違反を犯している場合には、労働基準監督署に通報すれば適切な対処をしてくれます。
アルバイトでも労働基準法が適用されます。賃金、労働時間、休暇、解雇などの労働条件や、募集・採用、いじめ、嫌がらせなど、労働に関する困りごとがあれば、都道府県労働局に相談できます(相談無料)。
参考
労働条件に関する総合サイト(厚生労働省)>相談機関のご紹介:https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/soudan/
■不審者・性犯罪から身を守るために
性犯罪は、ほとんどの場合、人通りの少ない時間と場所に被害者が一人でいるときに発生する傾向があります。主な手口としては以下のようなものがあります。
・携帯電話やスマートフォンを操作しながら歩く被害者の後方から突然抱きつく。
・マンションなどで、被害者の後をつけてエレベーターに乗り込み、その中でわいせつ行為をする。
・一人で歩いている女性に声をかけ、しつこくつきまとい、わいせつ行為をする。
・無施錠の玄関やベランダ窓から被害者宅に侵入する。
被害を防ぐために心がけておくこと
<外出時>
・明るい道、人通りの多い道を選んで歩く。
・携帯電話や音楽プレーヤーに集中せず、近づいてくる不審者や車に注意しましょう。
・知らない人にしつこく付きまとわれたら、すぐに「110番」しましょう。
<帰宅時>
・自宅の玄関扉の鍵を開ける前に、必ず周囲を確認しましょう。
・共同住宅の階段や踊り場などの共有スペースでの被害にも注意しましょう。
・エレベーター内では、いつでも非常ボタンを押せるように操作盤付近に立ちましょう。
不審者に遭遇したら…
素早くその場から離れ、安全な場所に避難し、すぐに警察に通報しましょう。「110番」することをためらう必要はありません!
■デートDV
デートDVとは?
交際している相手から振るわれる暴力のことです。暴力を使い、相手を思い通りに(支配)しようとします。身体的な暴力だけでなく、心理的暴力、経済的暴力、性的暴力など、様々な暴力が存在します。
「好きだから、気持ちを通じ合わせたい」「一緒にいたい」という気持ちと、「自分の思い通りに動いてほしい」「独り占めしたい」と相手をコントロールしたり、「自分のモノ」として扱ったりするのは全く違うことです。
一つでも当てはまったら、デートDVではないかと考えてみましょう。
<精神的な暴力>
・大声で怒鳴る、バカにする
・交友関係を制限する
・無視をする
・行動を監視・制限する
・メールなどをチェックする など
<身体的な暴力>
・殴る・たたく・蹴る
・腕をつかむ・ひねる
・髪を引っ張る
・物を投げつける
・刃物などを突きつける など
<経済的暴力>
・デート費用を全く払わない
・借りたお金を返さない
・外で働かせない・仕事(アルバイト)を辞めさせる
<性的な暴力>
・性行為を強要する
・避妊に協力しない
・嫌がっているのに裸などを撮影する
恋人は「自分のモノ」ではありません。自分の心やからだを大切にできるのは自分自身です。暴力を振るわれていい人など一人もいません。一人ではどうしたらいいか分からないとき、迷ったときには、各自治体のDV相談窓口へ相談してください。
参考
DV相談ナビ #8008(はれれば):https://www.gov-online.go.jp/article/202402/entry-5667.html#thirdSection
■ストーカー被害に遭わないために
ストーカー行為への対処法は状況によって異なりますが、次の3点が重要です。
・はっきりと拒絶の姿勢を相手に示す。
・電話や訪問の日時、手紙などの記録を残しておく。
・一人で悩まず助けを呼んだり、一日でも早く警察や信頼できる人に相談したりする。
身の危険を感じたら…
・防犯ブザーや携帯電話を持ち歩き、危険を感じたらすぐに近隣の人や警察に助けを求める。
・人気のないところは歩かない。人通りの多いところを歩く。タクシーなどを利用する。
・ドアや窓の施錠を徹底し、必ず相手を確認してからドアを開ける。
・可能であれば住所を変えるなど、相手から離れる。
ストーカー行為・DVは犯罪です。また、相手の心理状態によっては、どんどん行為がエスカレートし、被害が大きくなることがあります。一人で悩まず、家族・友人、警察相談窓口などへすぐに相談してください。
参考
・ストーカー被害を未然に防ぐことを目的とした、警視庁の情報配信ポータルサイト:https://www.npa.go.jp/cafe-mizen/
■学内での盗難に注意
学内での実際の被害例
・合評中、全員が別の教室に移動して無人になった教室で、置きっぱなしにされていた複数名の学生の財布から現金が抜き取られる盗難が発生しました。
・教室に他の学生が複数人いたので大丈夫だろうと、荷物を置いたまま教室の外に出てしばらくして戻ると、財布から現金が抜き取られていました。
・学園祭や卒業・修了制作展などの学園行事の準備中や後片付け中に、何人かの荷物をまとめて置いていたら、数名の財布から現金が抜き取られました。
大学では、所持品・貴重品の管理は自分自身で注意しなければなりません。学内だからと安心せず、貴重品(特に財布やスマートフォン)は常に携帯するようにしてください。学内では、外部から窃盗目的で侵入した者を見分けることは難しく、学内といえども十分に注意が必要です。学内で不審者を見かけたときは、すぐに教職員に知らせてください。
万が一盗難に遭ったら
キャッシュカードやクレジットカードはすぐに使用停止の連絡をし、必ず最寄りの警察署に連絡して盗難届を出すようにしてください。
■薬物(ドラッグ)の危険性 ―ゼッタイダメ!―
覚せい剤、大麻だけでなく、MDMA(錠剤型合成麻薬)や危険ドラッグなど、違法薬物の多様化が進んでいます。特に10代から20代の若年層への乱用拡大が顕著で、「危ない薬物」というよりも「ファッション感覚」で手を出してしまうなど、大変憂慮すべき状況になっています。
一度薬物中毒に陥ると、多くの場合完治は困難で、一生薬物依存症と付き合っていくことになります。このため、身体的な問題だけでなく、家庭の崩壊や悲惨な事件の原因にもつながります。たとえ1回の使用であっても乱用になり、れっきとした犯罪です。
薬物乱用が犯罪であることを理解し、誘われても断固として断ることが必要です。「面白いクスリがある」「みんなやってるよ」「一回だけなら平気」「痩せられるよ」などの誘いには絶対に乗らない、無責任な噂に惑わされないようにしましょう。
参考
文部科学省 大学生等に対する薬物乱用防止啓発資料「啓発用パンフレット」:http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/__icsFiles/afieldfile/2019/03/08/1344688_1.pdf